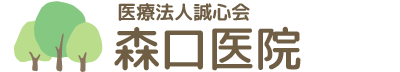子宮頸がんワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされているウイルスです。
子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。
HPVに感染してもほとんどの場合ウイルスが自然に排除されますが、排除されずに感染した状態が続くと上記のような病気になることがあります。
子宮頸がんについては、年間1万~1万5千人の女性の方がかかっています。
HPVには200種類を超える型(タイプ)がありますが、子宮頸がんになるリスクが高いものは14種類ほどで、特にHPV16型とHPV18型は、がんになるスピードが速いといわれています。
子宮頸がんにかかった日本人女性のうち、20~30代の少なくとも82.5%でHPV16型、18型の感染が確認されています。
HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。
副作用として発熱や、接種部分の痛み、腫れなどがあります。
また、恐怖や興奮をきっかけとした失神の報告もありますが、一方で、接種後に生じたと報告されている多様な症状についてはワクチン接種と直接の因果関係が乏しいとも報告されています。
日本国内で使用できるワクチンは、防ぐことができるHPVの種類によって、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。
サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができ、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。
シルガード9は、HPV16型と18型に加えて31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐと考えられます。
ただし、いずれのワクチンでも、ワクチン接種だけですべての子宮頸がんが防げるわけではありません。
性交渉の経験がある人は、必ず子宮がん検診を受けることが大切です。